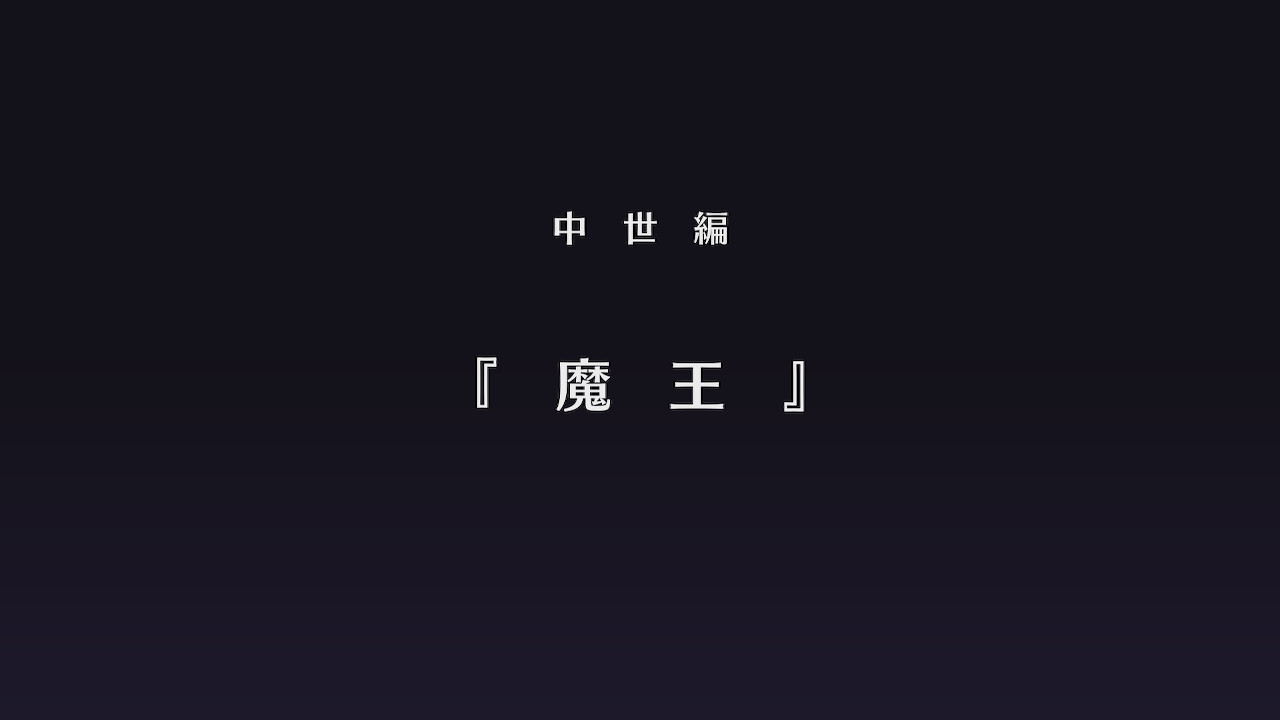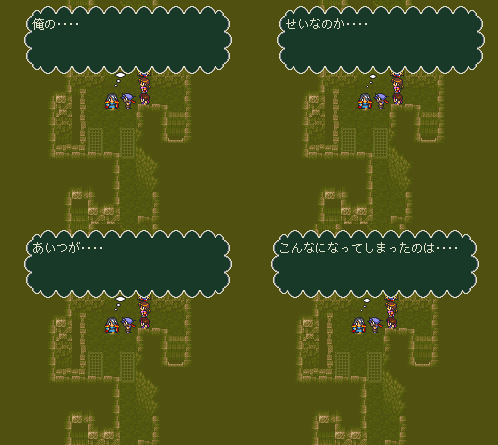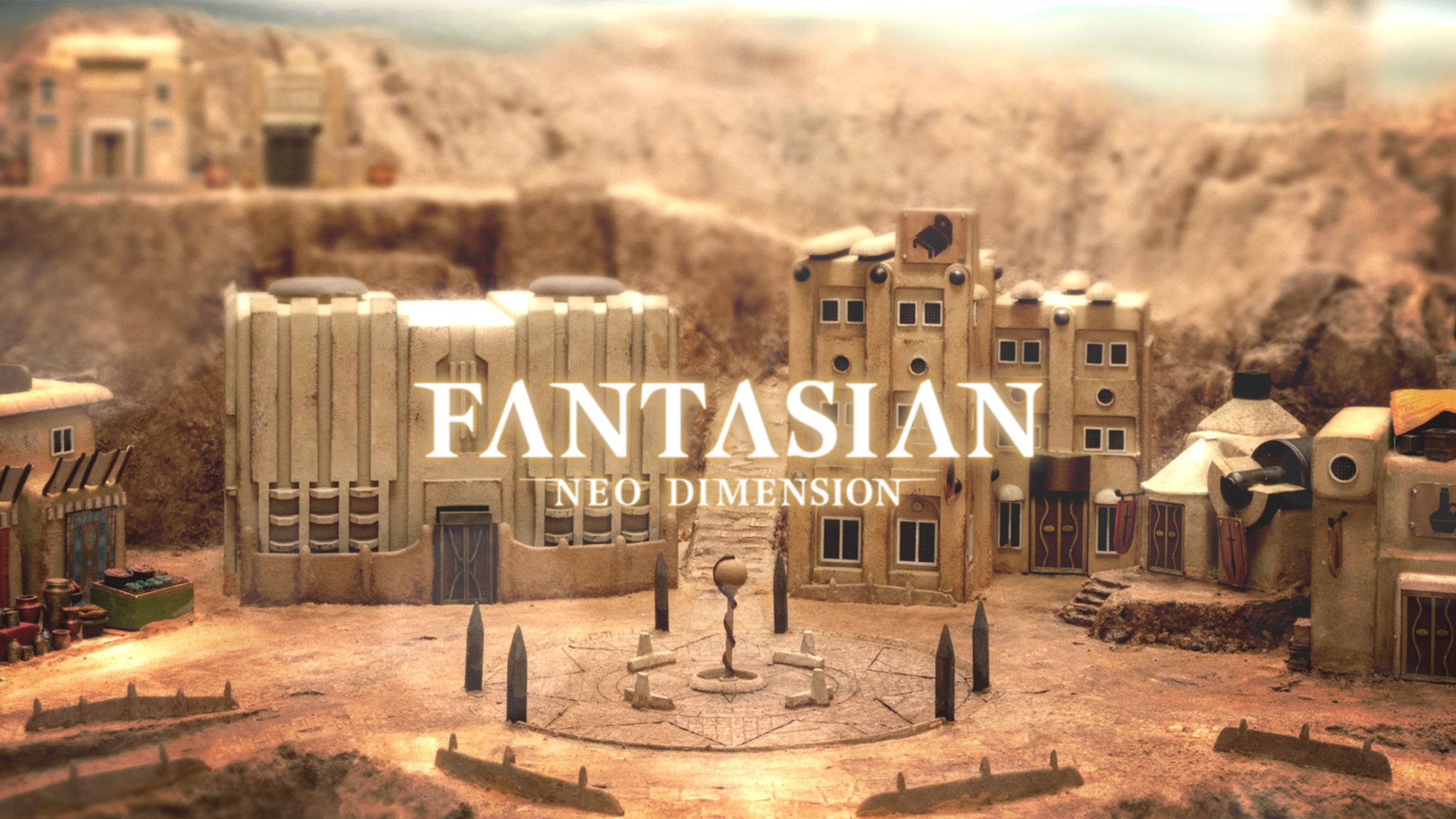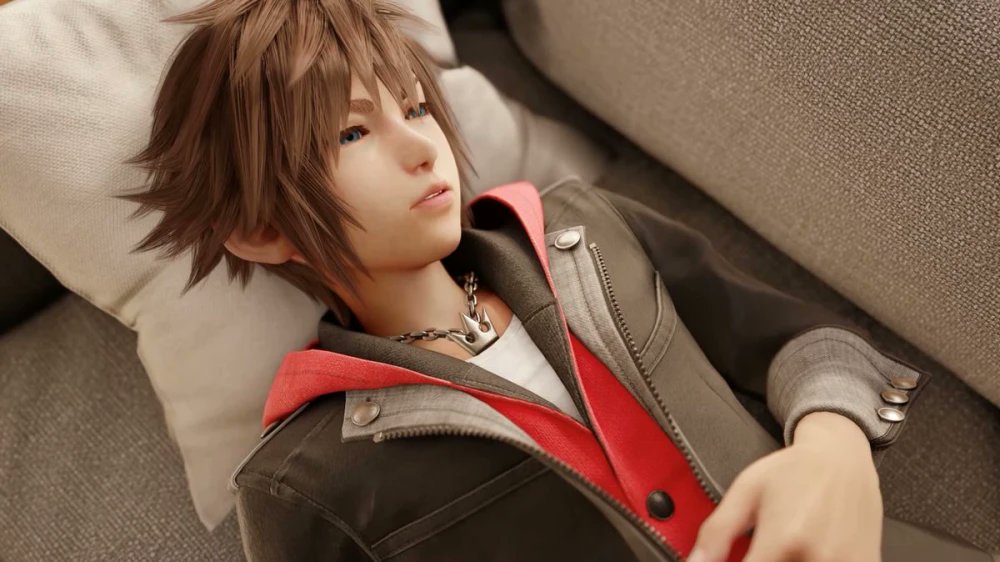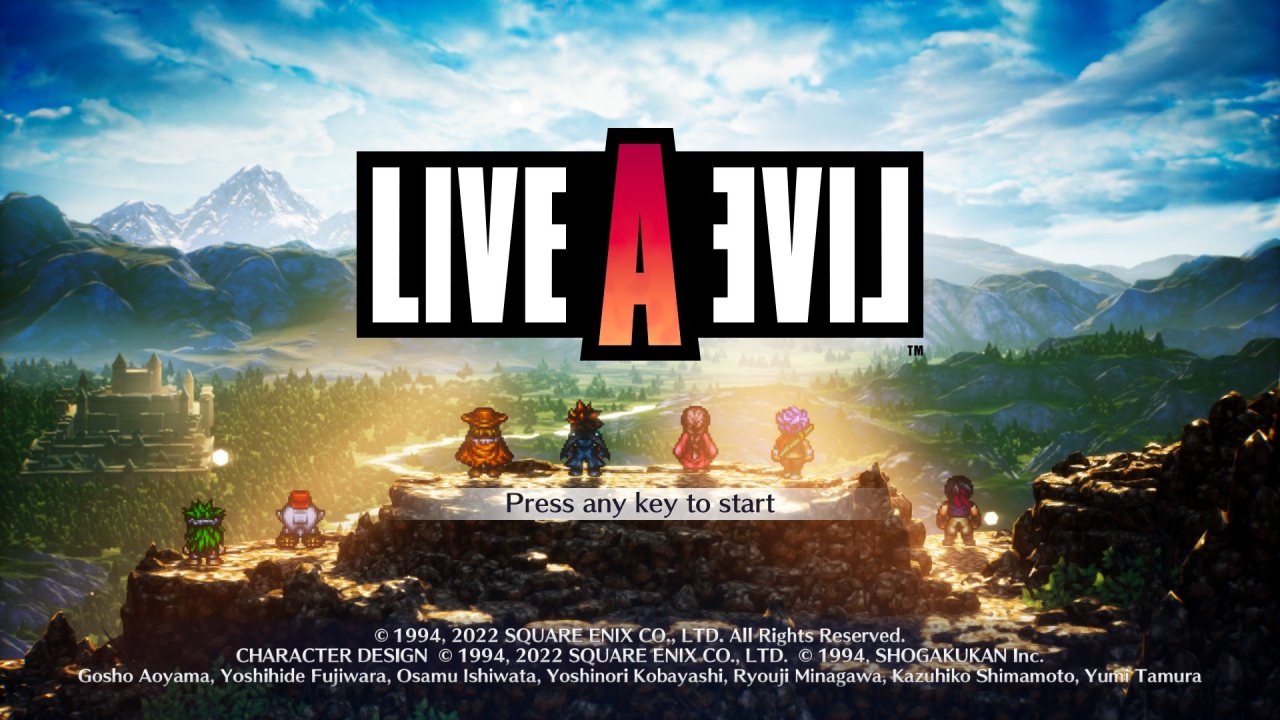
1994年にスーパーファミコンで発売され、2022年にNintendo Switch向けにHD-2Dでリメイクされた『ライブアライブ』は、時代や主人公が異なる7つの物語を楽しめるオムニバス形式のRPGとして知られています。
発売当時から「知る人ぞ知る名作」と評され、リメイク版も多くの注目を集めました。
しかし、一部で「つまらない」という意見も散見されます。
この記事では、「ライブアライブがつまらない」という批判的な意見と、それに対する反論を詳細に掘り下げ、ゲームの魅力や課題を多角的に分析します。
「ライブアライブがつまらない」という主な意見
リメイク版『ライブアライブ』に対する批判的な意見は、主にオンライン掲示板、レビューサイト、SNSなどで見られます。
これらの意見を整理すると、以下のようなポイントが浮かび上がります。
ストーリーが断片的で物足りない
『ライブアライブ』の特徴であるオムニバス形式は、各章が独立した短編ストーリーで構成されています。
一部のプレイヤーは、これが「ストーリーが断片的で深みに欠ける」と感じる要因になっています。
特に、各章のプレイ時間が1〜3時間程度と短めであるため、キャラクターや世界観への没入感が得られにくいという声があります。
また、7つの物語が最終的に繋がるものの、その繋がりが唐突に感じられる場合もあるようです。
ゲーム性のバラつきが大きい
各章は時代設定だけでなく、ゲーム性も大きく異なります。
たとえば、幕末編はステルス要素が強く、近未来編はビジュアルノベル風、現代編は格闘ゲームのようなバトルに特化しています。
この多様性が「統一感がない」「遊びづらい」と受け取られることがあります。
特に、ステルスや探索が苦手なプレイヤーにとって、特定の章がストレスになる場合も報告されています。
リメイクの追加要素が期待外れ
リメイク版では、HD-2Dの美しいグラフィックやフルボイス、音楽のアレンジが追加されましたが、これが逆に不満の原因となる場合もあります。
たとえば、オリジナル版のドット絵の雰囲気を愛していたファンからは「HD-2Dが現代的すぎる」との声や、ボイスの演技がキャラクターイメージと異なるという意見も。
また、ゲームバランスの調整が不十分で、難易度が一部で高すぎる、あるいは簡単すぎると感じるプレイヤーもいます。
価格とボリュームのバランス
価格に対するボリュームの不満も見られます。
リメイク版の定価は約6,000〜7,000円程度ですが、クリアまでの総プレイ時間が15〜20時間程度と、現代のRPGとしては短めです。
これにより、「価格に見合わない」「もっとボリュームが欲しかった」との意見が一部で挙がっています。
特に、近年の大作RPGに慣れたプレイヤーにとっては、物足りなさを感じる場合があるようです。
「つまらない」という意見への反論
一方で、『ライブアライブ』を高く評価する声も多く、批判的な意見に対しては以下のような反論が展開されています。
これらの反論は、ゲームの意図や魅力を理解することで、批判の背景を再評価する視点を提供します。
オムニバス形式の意図と魅力
「ストーリーが断片的」という批判に対し、擁護する側はオムニバス形式こそが『ライブアライブ』の最大の魅力だと主張します。
各章が短いからこそ、異なる時代やジャンルを手軽に体験でき、プレイヤーに多様な感情を呼び起こします。
たとえば、原始編のコミカルな雰囲気、SF編のホラー要素、幕末編の緊張感あるステルスなど、1つのゲームで複数の物語を楽しめるのは稀有な体験です。
さらに、7つの物語は最終的に中世編や最終編で繋がり、壮大なテーマである「人間の業」や「希望と絶望」を描き出します。
この伏線回収やテーマの深さは、初見では気づきにくいものの、クリア後に振り返ると感動を覚えるプレイヤーも多いです。
実際、レビューサイトでは「ストーリーの繋がりに驚いた」「後半の展開が神がかっている」との声が多数見られます。
ゲーム性の多様性は実験的な挑戦
ゲーム性のバラつきに対する批判については、「それこそが本作の革新性」と反論されます。
1994年のオリジナル版当時、RPGは一本道のストーリーや単一のバトルシステムが主流でした。
そんな中、『ライブアライブ』は各章で異なるゲーム性を採用し、RPGの枠を超えた実験的な試みを行いました。
リメイク版もこの精神を継承し、現代のプレイヤーに新鮮な驚きを提供しています。
たとえば、幕末編のステルスは「難しすぎる」との声もありますが、敵を倒さずにクリアする「0人斬り」や、逆に全ての敵を倒す「100人斬り」など、プレイヤーの選択で大きく展開が変わる自由度が魅力です。
同様に、現代編の格闘ゲーム風バトルは、シンプルながらも敵の技を覚える戦略性が評価されています。
これらの多様性は、プレイヤーに「次はどんなゲーム性が待っているのか」というワクワク感を与える設計なのです。
リメイクのクオリティと原作への敬意
リメイクの追加要素に対する不満については、HD-2Dや音楽、ボイスのクオリティを高く評価する声が反論として挙がります。
HD-2Dは『オクトパストラベラー』や『トライアングルストラテジー』で培われた技術で、ドット絵の温かみと3Dの立体感を融合させた唯一無二のビジュアルです。
多くのプレイヤーは、「SFC時代の雰囲気を残しつつ現代的に進化した」と絶賛しています。
音楽も、原曲を手掛けた下村陽子氏が監修し、フルアレンジで生まれ変わりました。
特に、中世編の「Wings」や最終編の「Megalomania」は、壮大なオーケストラアレンジで感動を誘います。
ボイスについては好みが分かれるものの、豪華声優陣(津田健次郎、緑川光など)の演技がキャラクターに新たな命を吹き込んだとの評価も多いです。
また、ゲームバランスの調整は、オリジナル版の難易度の高さを現代向けに緩和した結果でもあります。
たとえば、戦闘のテンポ向上やマップの視認性向上など、遊びやすさを重視した改良が施されています。
これにより、原作未プレイの新規プレイヤーでも楽しめる設計になっています。
価格とボリュームは価値観次第
ボリューム不足という意見に対しては、「質の高い体験が詰まっている」との反論があります。
15〜20時間のプレイ時間は、現代の大作RPG(50時間以上が一般的)と比べると短めですが、各章がコンパクトにまとまっており、冗長な要素が少ない点が評価されています。
プレイヤーからは「ダラダラした寄り道がない」「サクサク進むのが心地よい」との声も。
さらに、リメイク版は豪華なキャラクターデザイン(青山剛昌氏や島本和彦氏など7名の漫画家が参加)やフルボイス、豪華な音楽など、価格に見合うプレミアムな体験を提供していると擁護されます。
クリア後のやり込み要素(隠しボスやマルチエンディング)もあり、リプレイ性も確保されています。
プレイヤーの視点による評価の違い
『ライブアライブ』の評価が分かれる背景には、プレイヤーの期待やゲーム経験の違いが大きく影響しています。
以下に、異なるプレイヤー層ごとの視点を探ります。
オリジナル版をプレイ済みのファン
SFC版をプレイしたファンは、ノスタルジーを強く感じる一方、リメイクの変化に敏感です。
HD-2Dやボイスの追加を「原作の雰囲気を損なった」と感じる人もいれば、「現代に蘇った名作」と感動する人もいます。
特に、オリジナル版の粗削りな部分(難易度の高さや不親切な設計)が改善された点は、概ね好評です。
ただし、一部のファンは「原作の難易度こそが魅力だった」と物足りなさを感じる場合も。
新規プレイヤーの視点
原作未プレイのプレイヤーにとっては、HD-2Dの美麗なグラフィックや豪華なキャストが魅力の中心です。
オムニバス形式の斬新さや、短時間で多様なストーリーを楽しめる点は、特に忙しい現代のゲーマーに好評です。
ただし、RPGに長編ストーリーやオープンワールドを求めるプレイヤーには、コンパクトな設計が物足りなく映ることもあります。
ゲームデザインの文脈を重視する層
ゲーム史やデザインに興味があるプレイヤーからは、『ライブアライブ』の実験的な試みが特に高く評価されます。
1994年当時、オムニバス形式やジャンルの融合は革新的であり、現代のインディーゲームにも通じる先進性を持っています。
この層からは、「単なるリメイクではなく、RPGの歴史を振り返る意義深い作品」との声が聞かれます。
『ライブアライブ』の真の価値とは
『ライブアライブ』が「つまらない」という意見と、「名作」という評価の両極端を生む理由は、そのユニークな設計と挑戦的な姿勢にあります。
以下に、本作の真の価値をまとめます。
- 多様性と自由度: 7つの異なるストーリーとゲーム性が、プレイヤーに選択の自由と多様な体験を提供します。
どの章から始めるか、どの順番で進めるか、プレイスタイル(ステルスや戦闘重視など)も自由です。 - テーマの深さ: 各章は個別の物語に見えますが、「憎しみ」「絆」「成長」といった普遍的なテーマで繋がっています。
最終編での伏線回収は、プレイヤーに強いカタルシスを与えます。 - リメイクの完成度: HD-2D、音楽、ボイスの追加は、オリジナル版の魂を損なわずに現代にアップデートした好例です。
スクウェア・エニックスの技術力と原作への敬意が感じられます。 - ゲーム史的意義: 1994年のRPGとしては異例の挑戦を重ねた本作は、現代のゲームデザインにも影響を与えています。
オムニバス形式やマルチエンディングは、後の作品に大きなインスピレーションを与えました。
結論:あなたにとっての『ライブアライブ』とは
『ライブアライブ』は、完璧なゲームではありません。
ストーリーの断片感、ゲーム性のバラつき、ボリュームの少なさなど、批判される要素も確かに存在します。
しかし、それらの欠点は、本作の挑戦的でユニークなデザインの裏返しでもあります。
オムニバス形式の斬新さ、テーマの深さ、リメイクの美麗なビジュアルと音楽は、多くのプレイヤーに感動を与えました。
このゲームが「つまらない」か「面白い」かは、プレイヤーの期待や好みに大きく左右されます。
長編RPGや統一感のあるゲーム性を求める人には物足りないかもしれませんが、短編ストーリーの多様性や実験的なゲームデザインを楽しみたい人には、唯一無二の体験となるでしょう。
もしあなたが本作に興味を持っているなら、まずは1つの章をプレイしてみてください。
そこから広がる物語が、あなたの心を掴むかもしれません。
あなたにとっての『ライブアライブ』はどんな作品になるのか。
その答えは、コントローラーを握った先に待っています。